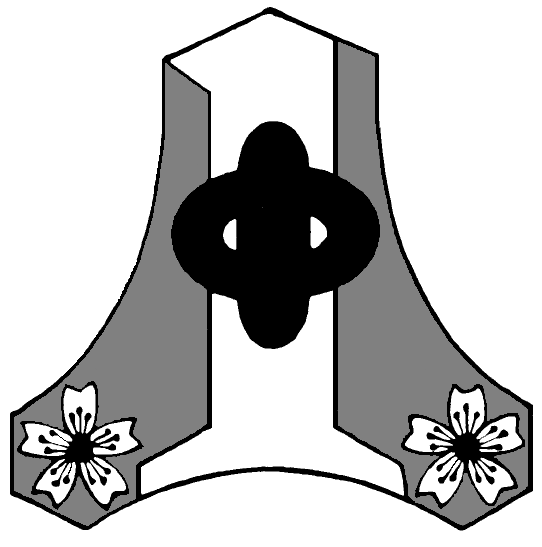『マイコプラズマ肺炎に関するQ&A』(厚生労働省)
- 公開日
- 2016/11/03
- 更新日
- 2016/11/03
お役立ち情報
既にテレビなどの報道でご存じのとおり、国立感染症研究所によりますと、最近の1週間のマイコプラズマ肺炎の患者の数が1999年の調査開始以来最も多くなり、流行の兆しがあるようです。軽い風邪に似ているので、風邪と診断されてしまうこともあるそうなので、注意が必要です。
保護者の皆さまには、マイコプラズマ肺炎に関してご理解をいただいていると思いますが、厚生労働省から出されている『マイコプラズマ肺炎に関するQ&A』(以下に内容を掲載)を参考に、更に理解を深めていただき、マイコプラズマ肺炎予防のご協力とお子さんへの指導をお願いいたします。
_________________________________
Q1 マイコプラズマ肺炎とはどのような病気ですか?
A1 マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ」という細菌に感染することによって起こる呼吸器感染症です。小児や若い人の肺炎の原因としては、比較的多いものの1つです。例年、患者として報告されるもののうち約80%は14歳以下ですが、成人の報告もみられます。マイコプラズマ肺炎は1年を通じてみられ、冬にやや増加する傾向があります。
Q2 昨年からマイコプラズマ肺炎が増えていると聞きましたが、どうしてですか?
A2 マイコプラズマ肺炎は周期的に大流行を起こすことが知られており、日本でも1980年代では昭和59(1984)年、昭和63(1988)年に比較的大きな流行があるなど、4年周期での流行が報告されていました。1990年代以降はかつて見られた大きな流行が見られなくなった一方で、平成12(2000)年以降は徐々に定点当たり患者報告数が増加傾向にあり、平成23(2011)年は年間の定点当たり累計報告患者数が、平成12(2000)年以降の最多報告数(2010年)を大きく上回りました。平成24(2012)年は第1週から第37週まで平成23(2011)年の報告水準を上回った状態が続いています。平成23(2011)年から平成24(2012)年にかけてこのような状態がみられている原因はよくわかっていません。
Q3 どのようにして感染するのですか?
A3 患者の咳のしぶきを吸い込んだり、患者と身近で接触したりすることにより感染すると言われています。家庭のほか、学校などの施設内でも感染の伝播がみられます。感染してから発症するまでの潜伏期間は長く、2〜3週間くらいとされています。
Q4 どのような症状が出ますか?
A4 発熱や全身倦怠感(だるさ)、頭痛、痰を伴わない咳などの症状がみられます。咳は少し遅れて始まることもあります。咳は熱が下がった後も長期にわたって(3〜4週間)続くのが特徴です。多くの人はマイコプラズマに感染しても気管支炎ですみ、軽い症状が続きますが、一部の人は肺炎となり、重症化することもあります。一般に、小児の方が軽くすむと言われています。
Q5 感染しないようにするために、どのようなことに注意すればよいですか?
A5 感染経路はかぜやインフルエンザと同じですので、普段から、手洗いをすることが大切です。また、患者の咳から感染しますので、咳の症状がある場合には、マスクを着用するなど咳エチケットを守ってください。
Q6 治療方法はありますか?
A6 抗菌薬(抗生物質)によって治療します。抗菌薬のうちでも、マイコプラズマ肺炎に効果のあるものは、一部に限られています。近年、マイコプラズマ感染症に通常使用される抗菌薬の効かない「耐性菌」が増えてきているとされていますが、耐性菌に感染した場合は他の抗菌薬で治療するなどします。軽症ですむ人が多いですが、重症化した場合には、入院して専門的な治療が行われます。長引く咳などの症状があるときは、医療機関で診察を受けるようにしましょう。
(注)マイコプラズマ肺炎は、マクロライド系などの抗菌薬で治療されます
_________________________________